子育てなどがひと段落して「また働きたい」と思っている50代の女性は結構いるのです。
しかし・・・
「この歳で仕事なんてあるの?」
「正社員は無理よね・・・」
求人をながめてはみるものの、その職種や条件を見てどうしてもあきらめモードになってしまいがちです。
事務職の求人ばかりに目が行っていませんか?
本日は経験がなくてもできる医療系や介護系の仕事に目を向けて解説していきたいと思います。
「50代からでも」「未経験でも」「資格がなくても」できる医療と介護の仕事について詳しく解説します。
50代でも全然正社員になれる可能性ありますよ!
目次
50代女性のお仕事事情は厳しい

50代になって転職や再就職を考えた時、「正社員」での雇用を考えている方には厳しい現実であることをお伝えしなくてはなりません。
50代女性でも求人はあります。が、そのほとんどの雇用形態はパート・アルバイト、良くて派遣社員と言うのが現実です。
「50代、60代活躍中」などと明記されている場合を除いて、たとえ自分のスキルや経験に当てはまるからといってやみくもに応募するのはやめておいたほうが無難です。
時間の無駄になりかねません。
派遣会社の進出
女性の社会進出が活発になったのも、完全失業率が下がったのも事実です。
しかし、50代女性の現実はそんなに明るいものではありません。
大企業などは特に50代以上の、特に女性の正社員の中途採用はゼロに等しいです。
50代に限らず、現実は大企業に勤める多くの女性は派遣社員などの非正規雇用なのです。
派遣会社が大きく成長
近年派遣会社は続々と増え、成長を続けています。
企業側も直接雇用よりも派遣会社に依頼するケースが以前に比べて段違いで増えました。
求人サイトに載っている案件も応募したら「実は派遣会社だった」、ということがよくあります。
派遣会社を使う企業側のメリット:
- 募集・採用にかかる手間や時間が省ける
- 派遣会社が一次面接的な役割をしてくれる
- 社会保険も健康保険も派遣会社が払う
- 雇用期限がある
こういった理由により正社員ではなく派遣での雇用が増えています。
派遣社員という働き方が十分に浸透したおかげで50代女性でも雇用機会が増えたのは確かです。
派遣社員は雇用期限が決まっているので「雇いやすい」ということも雇用が増えた理由のひとつです。
正社員で雇ってしまったら「あの人辞めてほしいな・・・」と思っても相当する理由が無い限りクビにできませんからね、会社にとっては厄介なのです。
派遣は雇い主にとって好都合なわけです。
50代女性が医療系・介護系の仕事を探すメリット

さて、ここから医療や介護の仕事を50代女性におすすめする理由などを解説していきたいと思います。
AIやITに仕事を奪われにくい
世の中の仕事はAIやITの発達によりどんどん自動化、機械化が進んでいますね。
受付や事務職、運輸業、飲食業でさえ技術の進歩とともに人員削減が徐々に進んでいます。
しかし、最新のテクノロジーではどうしてもまかなえない職場は医療や介護の現場なのです。
医療技術そのものには最新のテクノロジーなどがどんどん取り入れられていますが、患者など人間に関わる部分はどうしても対人間による看護や介護が必要です。
これから更に増えると思われる求人:
- 高齢者社会に伴う治療や入院の増加による医療現場での求人
- 病院、緩和ケア施設での医療、介護スタッフの求人
- 高齢者施設などでの求人
医療や介護の仕事は自動化が進む社会では「先進技術に職を奪われる心配がない業種」というだけで大きなメリットです。
50代からキャリア形成ができる
医療や介護の仕事は50代からでも第2のキャリアを築くことが可能な分野なのです。
50代から新たにキャリア形成ができる職種は多くありません。
医療や介護に関わる仕事は、50代女性が第2のキャリアが築ける数少ない分野です。

医療系は資格不要のポジションもあり、未経験でも応募できる求人は実は多いのです。
資格や経験がなくても「やる気」さえあれば採用率はかなり高いです。
将来役に立つ知識や経験になる
医療や介護の仕事のメリットは現場で得た知識や技術の経験は将来役に立つことです。
50代になると親が高齢になっている状況であることが多いと思います。
「親の介護をする」日が突然やってくるかもしれません。
医療の現場で仕事をする、患者と接する、ことで小さな知識や技術が積み重ねられていきます。
親だけでなく自分が入院した時などに役に立つことを仕事から学べることもあるでしょう。
今まで何となくしか考えたことのない「生きる」または「病気」や「死」ということに対して、仕事をすることできっと真剣に向き合うきっかけにもなることでしょう。
50代からでも始められる医療・介護系のキャリア

では具体的にどんなポジションが資格や経験なしで働けるチャンスがあるのか見てみましょう。
ここではパートやアルバイトではなく、「第2のキャリア」としてフルタイム「正社員」で働くことを前提としてお話をします。
看護助手
看護助手の仕事は看護師の補助をしたり、患者のお世話をしたりする仕事で病院やクリニック、介護施設などが主な勤務先となります。
看護助手は資格は不要ですが、注射など医療行為はできませんので、基本的に看護師や医師などの補助的な仕事をします。
看護助手の仕事内容
看護助手の仕事は主に3つの業務になります。
- 看護師や医師の補助業務
- 患者のケア業務
- 環境整備
順番に仕事内容を説明していきますね。
看護師や医師の補助業務
外来か病棟勤務かで業務内容は異なりますが、入院施設のある病院では看護助手は主に病棟に配置になることが多いです。
ただ、病棟勤務であっても外来やリハビリなどに患者を連れて行くなどすることが頻繁にあるので病院全体を大まかに把握しておく必要はあります。
病棟では医師の指示ということはあまりありませんので主に看護師の指示のもと、必要な補助業務をこなします。
このため、入社直後は、看護助手の先輩だけでなく看護師からも直接指導を受けることが多いです。
処置に必要な機材を用意したり、注射や採血、吸引などの際の補助作業など、看護師が作業しやすいように作業の補助をします。
患者のケア業務
病棟では入院患者の食事介助や、入浴介助、おむつ交換など入院患者の身の回りのお世話をします。
床ずれ予防のために体位交換など、看護師と共に入院患者のケアをする作業も日常的にあります。
また、見守りが必要な患者の検査やリハビリ、トイレへの付き添いなども行います。
環境整備
病院の規模や体制により仕事内容は大きく変わってきます。
病院にはとにかく医療器具を含め備品が多いため、その管理・補充は主に看護助手が行っています。
その他、医療器具の洗浄なども看護助手の仕事です。書類の整理などの業務も含まれる場合もあります。
病室の清掃は清掃スタッフがやることがほとんどですが、小さな病院では看護助手が一部行っている場合もあるようです。
環境整備の仕事とは院内、病棟内を清潔に保ち、医療スタッフが仕事をしやすい環境、患者ができるだけ快適に過ごせる環境を整える仕事です。
看護助手の勤務形態
病院によって2交代、3交代、4交代とその勤務形態は異なります。
病棟勤務であれば看護助手も夜勤シフトは組まれています。
ただ、未経験から始める場合は最初は夜勤は無いと考えてよいでしょう。
慣れてきたら夜勤を組み込むと給料がだいぶ良くなりますし、雇用主側もそれを求めていることが多いです。
第2のキャリアとして築いていくつもりであれば、ゆくゆくは夜勤ができる方向で考えていた方が良いでしょう。
50代でも正社員になれるチャンス
看護助手をおすすめする理由は何と言っても看護助手はどの職場も40代や50代が多い、ということです。
そして看護助手の仕事はパートや派遣だけでなく正社員になれるチャンスがあることです。
正直言って看護助手は楽な仕事ではないので20代、30代の若い世代の離職率は実は高めです。
若ければ他に割りの良い仕事がたくさんありますから、仕事に慣れた頃に辞めてしまう、というケースが非常に多いのです。
一方、40代、50代は仕事の選択肢が多くありませんので、「辛抱強い」ということも病院側も分かっています。
最初はアルバイトや派遣での雇用であっても、きちんと仕事をしていると病院や施設側の方から「正社員」を打診してくることは実はまれではありません。
正社員ねらうなら小・中規模病院
中・小規模の病院は院長や事務スタッフが身近な存在であったり、地域に根付いていたりして経営や雰囲気もアットホームなところが多いです。
そういったところは「正社員」をねらいやすいです。
おおっぴらに募集していなくても院内に募集案内がちょこっと貼ってあったりします。
小規模な病院ほど急な欠員が出るとすぐに補充しないと業務に支障が出るくらい看護助手が足りていないところが多いのです。
仕事に慣れてきたら、親しくなった看護助手や看護師に「正社員になりたい」ということを日頃からアピールしていくことも大切です。
こんな人がいます:
- IT系企業で定年退職後に派遣で看護助手の仕事を始めて、2年後に正社員になったという60代女性
- 医療事務を10年以上勤めた後、退職し、ほぼ10年振りの仕事復帰で看護助手に。アルバイトで入ったが、仕事ぶりが認められ1年後には正社員のオファーをもらった50代後半の女性
- 仕事経験は派遣で事務職のみ。50代になって未経験で看護助手に応募。2つ目の病院で正社員として入社した54歳女性
介護スタッフ
介護の現場も病院同様に万年の人手不足が加速している分野です。
特別養護老人ホームなどの高齢者施設、デイサービスセンター、病棟などが主な勤務先になります。
介護スタッフは有資格者であればなお良いのですが、人員不足もあって無資格・未経験でも積極採用しているところが多いです。
そして仕事をしながら介護の資格を取る人も数多くいます。
介護スタッフの仕事内容
介護スタッフは介護助手や介護補助者といったタイトルで働く施設によって名称は異なりますが、基本的に有資格者の補助的な業務になります。
(以下、無資格で働く介護スタッフを介護補助者とします。)
後述しますが、介護職は仕事をしながら資格が取れますので、介護の仕事をするなら働きながら資格取得を目指すことをおすすめします。
介護補助者の主な仕事:
- 有資格者の補助業務
- 生活援助業務
- 事務作業
- 送迎業務
基本的に看護助手と同じく有資格者の補助的な作業がメインになるのですが、大きな違いは病院よりも事務作業が多めであること、送迎業務が含まれることがある、ということです。
有資格者の補助業務
施設内には多種の有資格者が働いています。
介護補助者は施設入居者や患者の食事、入浴などの介助、おむつ交換など有資格者の指導のもとに身体介護業務を行います。
職場により多少差はありますが、概して高齢者や体の不自由な方のお世話をすることが多いため、車椅子やベッドなどへの移乗補助なども日常的な業務に入ってきます。
生活援助業務
施設の利用者の日常をサポートする業務で、その範囲は幅広く、施設や病院により内容はまちまちです。
食事の準備や片付け、シーツ交換、部屋の掃除の他、買い物や洗濯なども業務として行う場合もあります。
その他、施設のイベント開催やレクリエーションの準備などもこの業務に入ります。
事務作業
勤務する施設によっては事務員や受付を置いているところもありますが、小規模な施設などは介護スタッフが事務や受付を兼ねているところが多くあります。
電話や来客応対から、郵便物の管理・発送、備品の管理なども介護補助者を含む介護スタッフがしています。
資格が無くてもできる仕事は積極的に介護補助者が行うと良いでしょう。
送迎業務
病院や滞在型施設の場合は不要ですが、通所でデイサービスを行う施設の場合、採用条件のひとつに要普通運転免許というところもあります。
こちらも施設の規模によって差がでるところかもしれません。大手などは送迎担当者を別で雇っていますが、小さなところは介護スタッフが様々な仕事の掛け持ちをしている場合もあります。
介護補助者の勤務形態
入居設備のある施設であれば基本的に病棟と同じ様なシフトが組まれると思います。
施設により、2交代、3交代、4交代という感じで異なります。
未経験で無資格の介護補助者のアルバイト、パート、派遣社員などは最初は夜勤はないと考えて良いでしょう。
病棟の看護助手同様に介護補助者も各施設も夜勤のできる人材を欲していますのでゆくゆくは夜勤ができることが望ましいです。
高齢化社会に伴い年々入居者は増える傾向で、介護補助者の求人案件は増えています。
働きながら取得できる介護の資格
50代から介護の仕事を第2のキャリアとして築いていきたいと思ったなら資格取得を考えましょう!
実は介護職の資格には「50代からでも、働きながらでも」取れる容易なものがあります。
資格を取得しておくと正社員になりやすく、有利な転職や昇給につながります。
次にご紹介する介護の資格は受講さえすれば合格率はなんとほぼ100%。
取得しやすいにも関わらず、取得しておくと就職・キャリア形成に有利、というなんともお得な資格です。
介護の資格について
介護の仕事をするのであれば是非取得しておくべき資格をご紹介します。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
これらの資格は最短1ヶ月の通学で取得でき、しかも合格率が高い資格です。
多くの学校がオンライン授業と併用で学べるようになっています。
資格を持っていると給与面でも優遇されますし、専門職として働くモチベーションにもなります。
仕事をしながらでも資格取得が目指せるので介護や医療の仕事に興味のある方は取得しておくと良いでしょう。
介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
所定のスクールなどで介護の基礎知識やスキルを身につけるためにカリキュラム履修し、修了試験に合格すると得られる資格です。
最短1ヶ月で資格を取ることができます。
スクールでは介護職に必要な身体介護と生活援助についての知識や技術学びます。
カリキュラムを履修すればほとんどの人が合格します。
| 受講時間 | 130時間 |
| 講義 | 40時間 |
| 実技 | 90時間 |
| 実習 | 無し |
| 資格試験 | 有り |
介護福祉士実務者研修(旧ホームヘルパー1級)
介護職員初任者研修よりも更に実践的なスキルや知識を身につけるための資格です。
無資格でも受講できますが、介護職員初任者研修の資格を持っていると受講時間が少なくて済みます。
カリキュラム修了後に資格試験は義務付けられていないのできちんと履修すれば資格がもらえます。(※学校によっては試験を行っているところもあります)
| 保有資格 | 無資格 | 介護職員初任者研修資格保持者 |
| 受講時間 | 450時間 | 320時間 |
| 研修科目 | 20科目 | 11科目 |
| 受講期間の目安 | 約6ヶ月 | 約4ヶ月 |
| 修了試験 | 不要 | 不要 |
介護の資格でキャリアを築く
介護福祉士実務者研修の資格は介護福祉士国家試験の受験資格のひとつになります。
この資格を取得し、実務経験を3年積むと介護福祉士国家試験を受験することができます。
介護福祉士国家試験の資格をとることで、訪問介護事業所で配置が義務付けられている「サービス提供責任者(サ責)」になることができるのでキャリア形成に大きく有利に働きます。
介護の仕事でキャリア形成を目指す方は、介護の現場で働きながらまずこの2つの資格取得(介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修)を目指すと良いでしょう。
資格取得の流れをまとめると以下のようになります:
↓
②介護福祉士実務者研修
↓
③介護福祉士(国家資格)
スクールは10万円くらいからで通えます。また、教育訓練給付金制度があり、助成金制度を利用することで自己負担が少なく済みます。
ご参考までに講座料金比較のサイトを載せておきます。
50代女性の転職や再就職は定年のない仕事選びを

50代の女性はちょうど子育てなどがひと段落する年齢ということもあり、自分の人生を見つめ直す人が多いのです。
転職や再就職もその見つめ直しのひとつです。
今回ご紹介した医療や介護の仕事は多くの50代が活躍する仕事の分野です。
また彼女たちの多くが40代、50代になってから転職、再就職、そして資格を取って活躍しています。
中年期以降から新たにキャリア形成できる仕事は他にはほぼ無い、と言って良いでしょう。
50代から始める医療や介護の仕事の魅力まとめ
- 未経験・無資格でも始められる
- 正社員になれる可能性が他業種に比べダントツで高い
- 働きながら資格が取れる
- 定年のないキャリア形成ができる
そして今日ご紹介した介護の資格は受講さえきちんとすればほぼ100%の合格率なのです。ぜひ取得しておきましょう!
50代でもあきらめることなく第2のキャリア形成に役立つことを願っています。
医療事務は50代からのキャリア形成には不向き
さて、ここで同じ医療系で無資格でもできる仕事のなかでひとつだけ50代からのスタートには向いていないと思われる職種について簡単に述べておきたいと思います。
医療事務という仕事案件は求人サイトにも結構載っています。
40代、50代でも働けるチャンスがある仕事だと思います。
しかし、あなたが50代であれば、そのほぼ100%が「パート」「アルバイト」と思ってください。
無資格・未経験であれば100%です。
50代から正社員を目指す仕事としてはふさわしくない、と言い切れます。
医療事務の仕事は20代〜50代まで幅広い年代の方が活躍しています。
医療事務はパソコンスキル(ワード・エクセルは必須)が必要で、脳や目、体力の衰えが確実に反映される仕事です。
病院側もパソコンスキルがあり、体力、身体機能の衰えのない若手に働いてもらいたい、という思いは必ずあります。
医療事務は一般事務と違い医療保険制度や診療報酬の仕組みについて学ぶ必要がでてきます。
パートやアルバイトであれば無資格でも採用していること頃もありますし、専門知識は要求されません。
医療事務の資格にはいくつかありますが、いずれも合格率は60%程と難易度はやや高めです。

医療事務は50代から資格を取ってキャリア形成するには不向きな医療系のお仕事であると言えるでしょう。
50代から未経験で医療・介護系で働くための参考書籍
医療や介護の現場に入る前に読んでおくとためになる本をいくつかご紹介しておきますので参考にしてみてください。
求人に応募する前の一読におすすめの3冊です。
早引き介護のための医学知識ハンドブック
おすすめポイント:医学のごく初歩的な基礎知識や介護する際のポイントなどが載っています。介護現場で出会いそうな疾患の一覧であったり、日常の患者、入居者のケアの仕方など、家庭での介護にも役立ちそうな内容なので持っていて損しない一冊です。

アラフィフでヘルパーはじめました
おすすめポイント:アラフィフの何のとりえもない普通の主婦が介護の仕事を始めた、という作者自身の体験談。高齢者や認知症の人などとの付き合いから様々なことを学び、更には日本が抱える高齢化社会の問題を明るくコミカルにまとめたエッセイです。リアルな介護職の日常が見える貴重な一冊です。
改訂10版 看護補助者のための医療現場入門
著者:一般社団法人 千葉県民間病院協会 看護管理者会 (編集)、 菊地 薫(平和台病院 看護部長) (著)その他
おすすめポイント:今後更に需要が増えると考えられている看護助手(看護補助者)をターゲットにした貴重な参考書です。看護助手の業務内容や看護助手目線での医療現場を学べる本はほとんどなく、2022年9月に改定版として発売されたばかりの良本です。

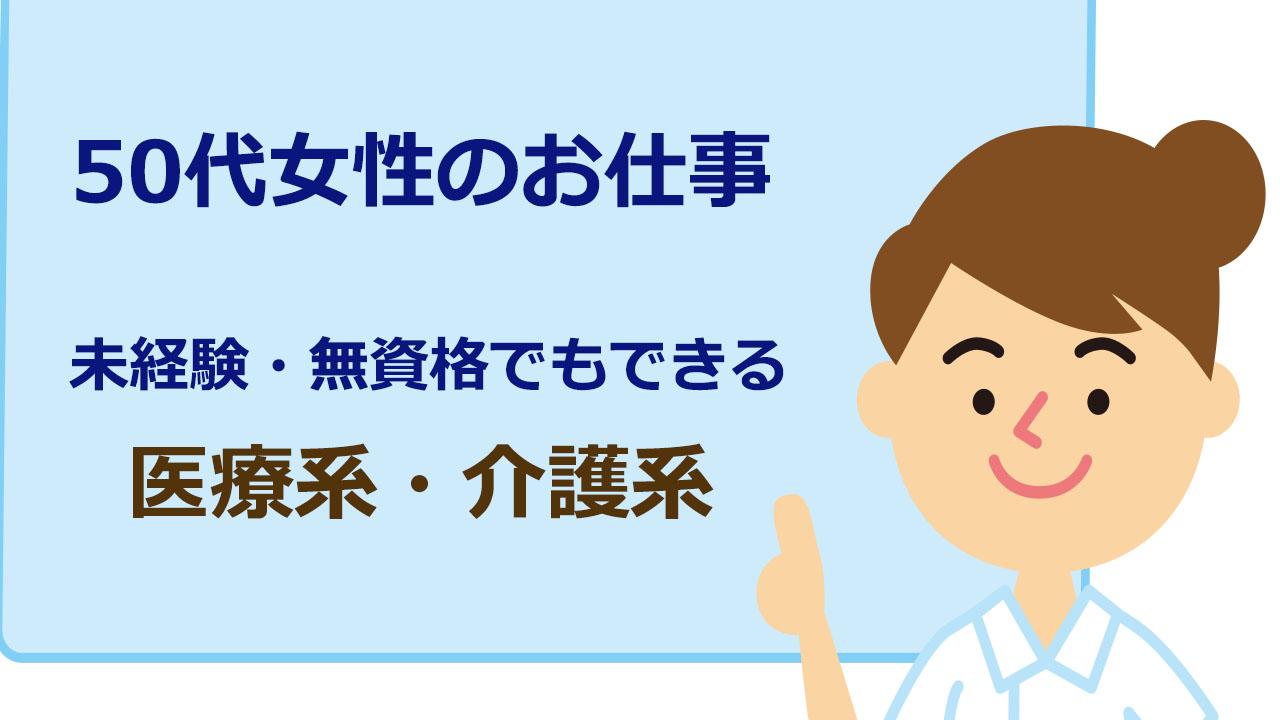







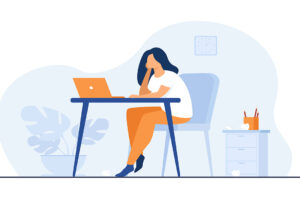






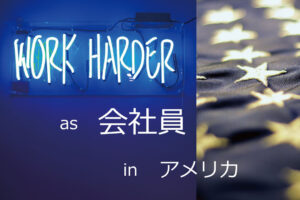
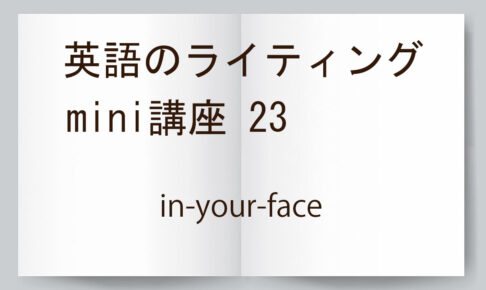
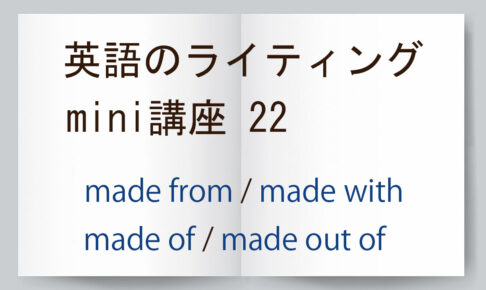
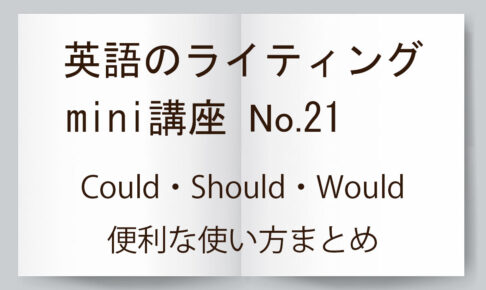
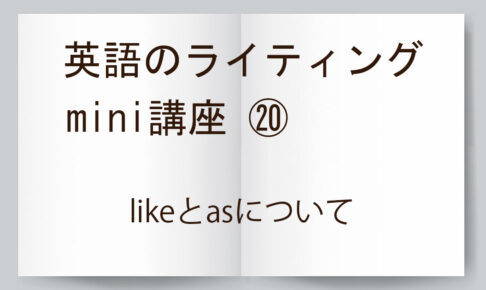


最近のコメント