こんにちは!
翻訳業をしているよっしーです。
今日は読み手に不安を与えない英文のライティングのコツについて学習しましょう。
「これってどういう意味?」
「これってこういう意味かな?」
英文を読みながらこんなことを考えている時はある意味迷子になってしまっているのです。
迷子になったら不安になりますよね?
この様に読み手に不安を与えるような書き方をすべきではありません。
ライターの意図が全ての読み手に同じ様に伝わる書き方を心がけましょう。
今日は読み手を不安にさせない英語のライティングのコツを少しお話ししたいと思います。
目次
迷いのない書き方を心がける
この章では「迷いのある書き方」「迷いのない書き方」を例を挙げて解説します。
迷いのある表現はmay beやprobablyなどの仮定の意を持つ単語だけで表すものではありません。
早速、下記の2つの英文の違いを指摘してみてください。
① Previously, anatomy is taught by textbook method, while now the clinical method is adopted.
② Previously, anatomy is taught by textbook method; now it is taught by the clinical method.
実は2つの英文には大きな意味の違いはありません。
しかし、①の英文は確信に欠け、読み手が「ほんとなのかな?」という不安を感じてしまう文章なのです。
一方、②の英文はライターが断言していることを読み手は感じるため、読んでいて安心する文章です。
読み手に不安を感じさせないライティングの3つポイント
例題の違いがイマイチ分からない、という方もいるかもしれません。
どんな単語や書き方に対して読み手が不安を感じてしまうのでしょうか?
上記の例文を題材に3つのポイントで解説していきたいと思います。
- カンマとセミコロンの違い
- whileが対比を弱める効果
- 同じ単語を繰り返し使って強調
それでは順に詳しく見ていきましょう。
カンマとセミコロンの違い
カンマは前後の節をただ単につなげているに過ぎません。
何かを羅列する時にはカンマで十分です。
ですが、②の英文の様にカンマの代わりにセミコロンを使うことで「対比」を強調することができます。
この場合、教科書と臨床を対比の関係に置き、解剖学は今、教科書に代わって臨床による学習に変化した、ということを強調する効果があります。
whileが対比を弱める効果
whileは学校や教科書などで「一方」や「〜している間」という意味として習ったのではないでしょうか?
そういった意味として、例題でも使っています。
そして、whileには「一息つく」効果があるのです。
一息つくことで対比の関係性を弱めてしまうのです。
「while」で一息いれることで、読み手はライターが「今は臨床学習だ」と言い切っていない、ライターの迷いを感じてしまいます。
読み手は「ん?まだ教科書もまあまあ使っているのかな?」と思ってしまうのです。
一方、②の英文のように「now it is」とライターが断言することで読み手は確信し、安心するのです。
同じ単語を繰り返し使って強調
例題では「〜による」という意味の「by」を前節と後節ともに使うことで対比を強調しています。
byの繰り返しによって読み手は「何なのか」を素早く対比、理解することができます。
前置詞のby や withの繰り返しは対比や強調の際に効果を発揮します。
2つの物事を対比したい場合、一方だけにbyやwithを使うと他方の存在が薄れてしまうので、両方にこれらの前置詞を使うと効果的です。
同じ動詞を繰り返す
②の英文ではtaughtを前節、後節ともに使っていますが、①ではadoptedがtaughtの代わりに後節に使われていますね。
違う動詞を使うことが効果的な場合もありますが、例題の場合では動詞を変えたことがかえって「断言していない」弱さを読み手に与える原因になっています。
同じ動詞を繰り返し使うことで2つの事柄の対比を強調しています。
前置詞と冠詞を正しく使って読み手を混乱させない
次に前置詞と冠詞の「読み手の混乱を避ける」書き方について少し触れたいと思います。
動詞の後に前置詞がないと意味が完成しない場合があるので気をつけましょう。
難しく考えず、「読み手がわかりやすい様に書く」ことを心がければ自然と前置詞が配置できるようになりますよ。
I need someone to talk.
この様な英文があったとします。
単に誰かと話したいだけなのか、誰かに何か話したいことがあるのか、など色々状況が考えられますよね。
ライターがどういう意図で書いた文なのかはっきりしません。
前置詞をつけることで意味が完成する
動詞の後に前置詞をつけてみましょう。
① I need someone to talk with.
(withを使うことで、誰かと話したい、という寂しさだったり、悲しさだったり、人恋しさの様な感情が表現できます。)
② I need someone to talk to.
(toを使うと何か話しておかなければならないこと、があるのかな、と思わせます。緊急性、切迫感に似た感情を表現できます。)
前置詞をつけることで状況がはっきりし、ライターの意図が読み手に伝わります。
もうひとつ例で比べてみましょう。
① His bizarre ideas are marked by disagreement and scorn for his subordinates.
② His bizarre ideas are marked by disagreement with and scorn for his subordinates.
①と②の違いは前置詞のwithの有無だけです。
withを入れることにより、彼のへんてこな考えが「誰」に賛同されなかったのかが明確化されます。
(この場合、subordinates)
更に、「scorn for」が熟語として成立していおり、このforはdisagreementにも併せてかけることはできません。
よってdisagreementにも前置詞が必要になるのです。
以上のことから、withは必ず必要です。
対象が人物ではなく、モノや事柄の場合はoverやaboutなどの前置詞が使われる場合もあります。
対象は何か、熟語なのかどうかで使われる前置詞は変わってきます。
前置詞が必要な単語は無数にありますが、以下、前置詞が必要な場合が多い単語の代表例です。
- disappointment
- hope
- dream
- challenge
- understanding
- difference
これらの単語に使われる前置詞はin, with, for, about, between, among, againstなどです。
文法は間違っていなくても前置詞が無いと意味が通じない場合があります。
気をつけましょう!
一貫性を出す(前置詞)
前置詞が無いと意味が通じない場合がある、ということを学びましたね。
ここで前置詞を使って事柄を羅列する場合について触れておこうと思います。
前置詞をどこに置くのか置かないのかのポイントです。
例)春、夏、秋、冬と季節を並べる場合
(間違った書き方)
in spring, summer, fall or in winter
(正しい書き方)
① in spring, summer, fall or winter
② in spring, in summer, in fall or in winter
簡単ですね!
前置詞の必要な単語や節の羅列をする場合:
前置詞を最初だけに使うか、全てに対して使うか、のどちらか、と覚えておきましょう。
春と夏のところだけin入れて秋冬は入れない、という様な使い方はしません。
このルールは季節や曜日に限ったことではありません。
in、on、with、aboutなどの前置詞を使った物事の羅列の際には気をつけましょう。
もし、単語の羅列が10個、20個など多い場合には最初だけに前置詞を配置する方が文章がスッキリします。
一貫性を出す:冠詞
物事の羅列時の前置詞について学んだついでに冠詞にも少し触れておきます。
冠詞とはaやtheのことですね。
単語を羅列をする場合、theやaを混合使用したり、付けたり付けなかったりすると読み手が混乱します。
一貫性を出す書き方をしましょう。
(間違った書き方)
the French, the Italians, the Chinese and Japanese
(正しい書き方)
the French, the Italians, the Chinese and the Japanese
My Favorite Coffee【但馬屋珈琲】

おつかれさまでした!
今日のmini講座のレッスンはちょっと難しかったですか?
繰り返し読んで理解しておくと英語のライティングにきっと役に立ちますよ!
さて、今日のa cup of coffeeは但馬屋珈琲のオリジナルブレンドです。
見た目は苦そうだけど、全くそんなことなくてコクがあっておいしいです。
ねっとり濃厚なチーズケーキとの相性が抜群です。
レアチーズっぽいけどベイクドチーズケーキなんですよね~。
ーーーーー
但馬屋珈琲(東京都内に数店舗あります。)
※新宿の小田急百貨店内の店舗は2022年10月に閉店。めちゃ残念!!
公式サイト:https://tajimaya-coffeeten.com/
ーーーーー
See ya next time!
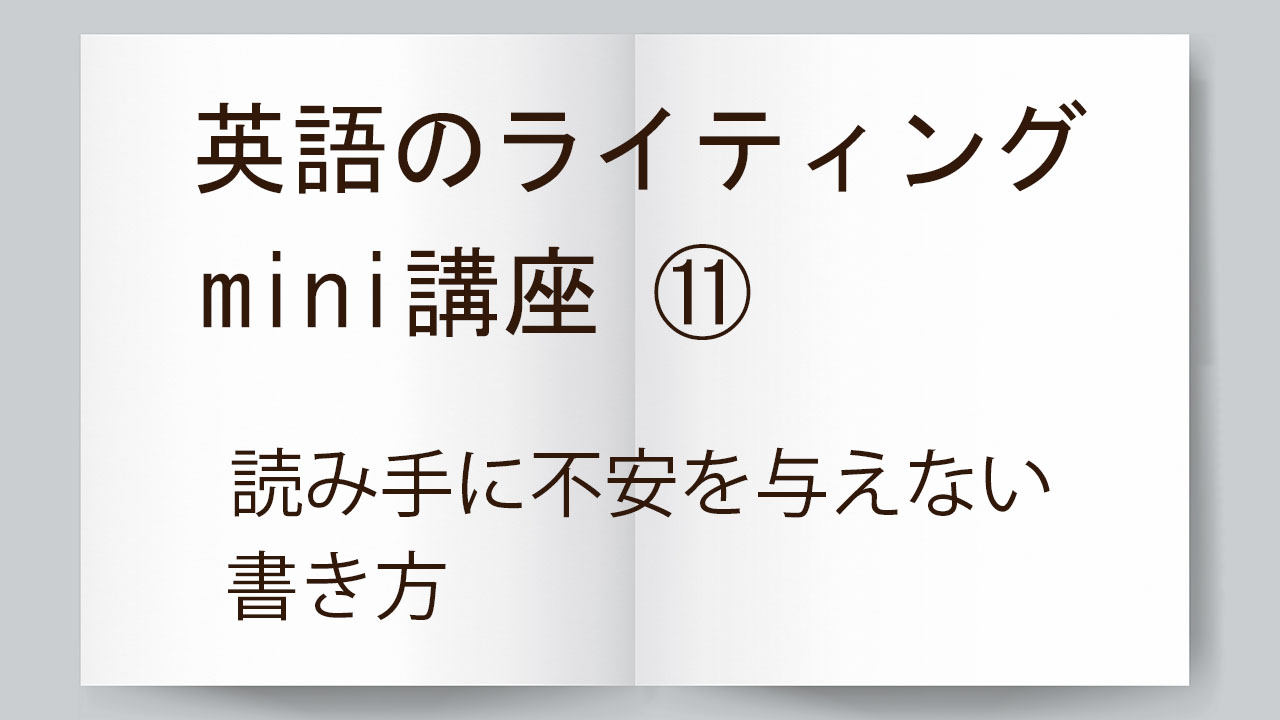
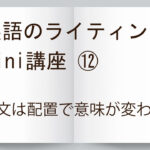
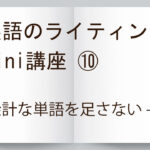
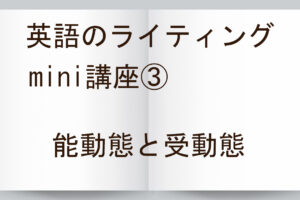

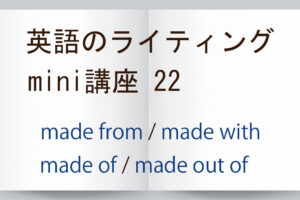
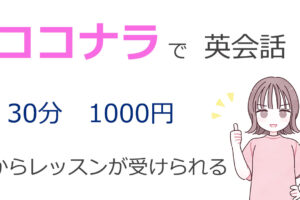
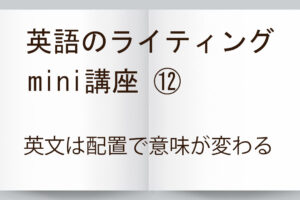
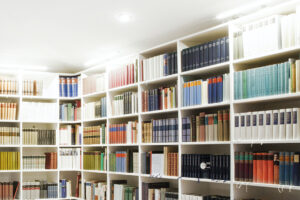


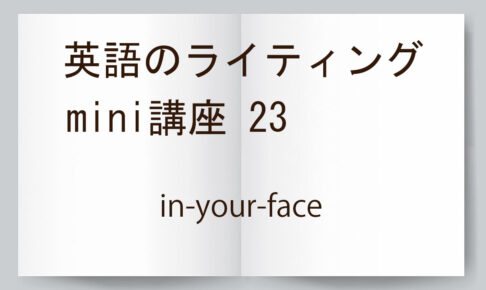
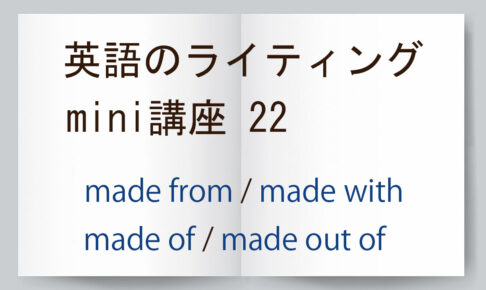
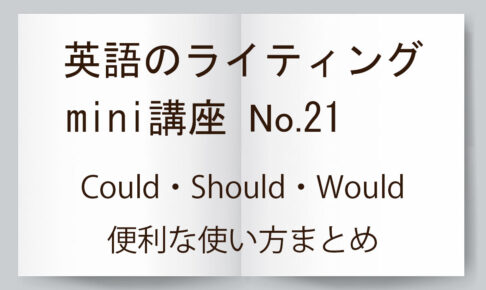
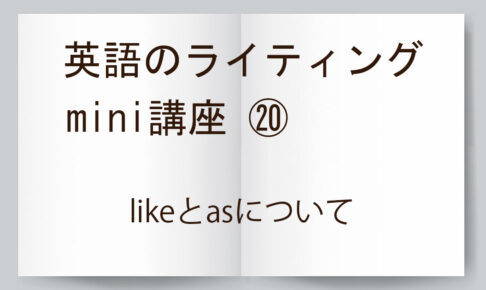


最近のコメント